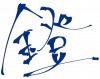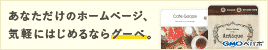ブログ
お墓のこと
最近は、いろんな事が自由に選べる時代。
お墓もその一つです。
長男が家督を継ぎ、先祖代々のお墓を守っていく
一昔前は、それが普通でした。
もちろん、今もそのような風習を粛々と受け継がれている方はいらっしゃいます。
一方で、新しい形のお墓を求める方も増えてきています。
その理由としては、少子化や生涯未婚率の上昇などの時代背景もうかがえます。
自然葬
海に散骨する海洋葬や樹木葬などが注目を集めています。
お墓が無いので管理の心配をしなくて良いこと。
樹木葬については、絶えず誰かがお参りに来るので寂しい思いをしなくて(させなくて)良いこと。
永代供養
霊園や寺院などが管理・供養すること。
宇宙葬
ご遺骨をロケットや人工衛星に乗せて打ち上げます。
種類は「月面供養」「流れ星供養」等。
バルーンに入れて飛ばす「バルーン葬」というのもあるらしいです。
手元葬
ご遺骨の一部を手元に残すこと。
コンパクトなので場所も取らず、お仏壇を置く場所が無いご家庭にも喜ばれます。
今は、便利で合理的な世の中になりました。
子どもたちにも迷惑をかけたくない、手をわずらわせたくないという方も増えてきています。
時代とともに人の考えや価値観は変化して行きます。
ただ、いつの時代も変わらないのは
ご先祖様のおかげで今の自分が存在する事です。
そのご先祖様に手を合わせ感謝をすること
その教えを親から教わったように、後世に伝えていくのは自分です。
この事を、私は和尚様からききました。
無駄な事なのか、わずらわしい事なのか、必要なことなのか、望むことなのか
ご先祖様に感謝をすることを教えてくれた、親や和尚様に感謝しています。
墓石屋さんが、「最近は墓じまいばかりだ」とおっしゃっていました。
どんな形のお墓にしても、供養にしても、大切なのは心の在り方。
長男が当たり前に家督を継いでいた時代には
ご先祖さまや家族への深い想いがそこにあったのだと思います。
生前整理のやり方
生前整理とは、元々財産の整理という意味合いで使われていたそうですが
最近は身の回りの整理、つまり、片付けをするという事で使われています。
片付け・・・やろうと思ってもなかなかできないものです。
意外とエネルギー使いますよね。
いろいろ自分に言い訳していろんな理由をこじつけて先延ばしにしてしまいがちになります。
遺品整理の作業でご依頼者様宅に伺うと、結構な物の量があります。
息子さん、娘さんから親御さんの家を片付けて下さいとのご依頼が多いのですが
みなさん物の多さに本当に困っていらっしゃいます。
「もったいない」と使わない物を残しておくと、片付ける方に相当な負担をかけることになります。
というわけで、生前整理はがんばって少しずつやってしまいましょう!
片付けのコツは、片付けようと思わないことです(^^)/
んんん???矛盾してますね…?
言い方が違うかも知れませんが、片付けるのではなく「捨てる」のです!
片付けるという事に専念してしまうと「右の物を左に置く」「上の物を下に置く」
といった具合に物は減りません。
服を処分しようとしたけど「高かったから」「痩せたら着れるから」と、
結局洗濯してタンスにしまい直した方。
その服を着る時は来るのでしょうか?
使わないけどいつか使うかも知れないからと、倉庫を借りてまで物を取っておく方。
借り賃が月3万だとしても、1年で36万円。
その倉庫の物を使う場面はあるのでしょうか?
『捨てる』方向にシフトすると、物が減るので勝手に片付きます。
使わないものは捨てる。物を使っていた時の感謝の気持ちを込めて捨てるのです。
フリーマーケットやネット販売を利用するのも良いですね。
そして、もう一つのコツは狭い所から片付ける事です。
例えば、トイレ。トイレは家の中でも比較的狭い所なので、あまり気負わずに取り掛かることができます。
トイレの中のいらない物を捨てるだけでもスッキリします。
トイレットペーパーのストックもトイレの中に置ける分だけにしましょう。
物が減り、家の中が片付くと新しい風が流れます。部屋も気分もスッキリして気持ちが前向きになります。
少しずつ、引き出しを一つずつでも良いので無理のない範囲で生前整理を始めてみませんか?
終活は必要なのか
終活は必要かときかれたら、「必要」だと答えます。
でも、必ずしもやらなければならないというものではありません。
人それぞれ考え方は違って当然です。
生きている間に、なぜ死ぬことばかり考えないといけないのかと、
もっと楽しいことを考えて生きていたいと思う気持ちもよくわかります。
終活は、主に身の回りの整理を行うことがメイン作業になります。
それを、「死に支度」と捉えるか「生きる目的」と捉えるかでも違ってきます。
死に支度を普段の生活でやりたい人はおそらく少ないでしょう。
「断捨離」にしても、無駄だと思える物全てを捨てなさいと言われると到底出来ません。
他人には無駄に見えるものでも、自分には癒しになるものが存在します。
「遺言書」は、相続を簡単にするご家族への思いやりです。
自分が亡きあとは好きなようにしてね
と、いうのが果たして良いことなのか疑問も残ります。時と場合にもよります。
自分にとって、居心地の良い暮らしをする。
家族やまわりの大切な人への配慮をする。
後悔や心残りを少しでも減らす。
それが「終活」で、人生を豊かにするものだと思っています。
終活は、強要されるものではありません。
自らの意思でするものです。
遺品整理

先日、親御さんの遺品整理をされている方のお話を伺いました。
その方は亡くなられたご両親の長女で、ごきょうだいが遠方にいらっしゃるため
おひとりで遺品整理をされているそうです。
彼女は普段から部屋の整理整頓が苦手だということだったので、
さぞかし大変な思いをされてるだろうと推察し
大変なときはいつでもご相談くださいと申し上げました。
すると、彼女はこう言われました。
「ありがとうございます。でも、私は自分でやりたいんです。
少しずつしか進まないけど、片付けているうちに母の気持ちが伝わってくるんです。
部屋に洗濯物干し場を無理やり作って、なんでこんな物作ってごちゃごちゃさせるんだろうって
あの頃は母の怠慢だとしか思ってなかったのですが
今考えると、体がきついからここでしか干せなかったんだ。私たちに少しでも迷惑かけないように
母なりに工夫していたんだと思うんです。」
遺品整理をするのは大変です。
でも、遺品整理をした人じゃないと伝わらない親(亡くなられた方)の気持ちというのは確かにあります。
その気持ちは、おそらく遺品整理をしていない人にはわかりません。
そして、その気持ちを感じ あらためて亡くなられた方に感謝の意を表すことも 供養になるのかなと思っています。
人には様々な事情があるので、遺品整理がしたくてもできない方も、もちろんいらっしゃいます。
自分の置かれた状況で行動を決めるしかありません。
ただ、今回はあらためて遺品整理について考えさせられた出来事でした。
なぜ生前整理をするのか
断捨離
という言葉はご存知でしょうか
そもそも、断捨離という言葉は「ヨガ」からの由来だと言われています。
不必要なものから断つ事、捨てる事、執着から離れる事
それを片付けに応用したのが今の断捨離だそうです。
生前整理とは
元々、相続等の問題を減らすべく、主にお金関係の整理という事で使われていたみたいですが
今は身の回りの整理という意味合いが濃くなっています。
このように、生前整理と断捨離は全く別の物ですが
今はどちらも片付けという言葉でひとくくりになっていますね。
なぜ、生前整理をするのか?
一言でいうと、まず、「遺品整理」が楽になるからです。
遺品整理は誰がやるのでしょう?
それは、遺されたご親族がやることが圧倒的に多いです。
実際に私たちが遺品整理に伺うと
押入には使わない布団や贈答品などがギッシリ。
タンスには長年着ていない着物や洋服がどっさり。
倉庫は行き場のなくなった物たちの集会場と、なっています。
この、トラック何台か分の遺品を片付けるのはご親族の方です。
子育てや仕事で毎日忙殺されていたり、病気でなかなか身動きがとれないでいたり
高齢で思うように体が動かない、そんなご親族の方です。
そして、今は物を捨てるのにお金のかかる時代です。
物が多ければ多いほどお金はかかります。
片付けをするのに、仕事を休んで、病気の体にムチ打って、お金は飛んでいく。
遺される大切なご家族に、そんな大変な思いはさせたくないですよね。
だから、生前整理は必要なのです。
「もったいない」なんて言ってる場合じゃありません。
「時期が早すぎる」なんて事もありません。
一日でも早く断捨離しませんか?
あなたの大切な人のために。